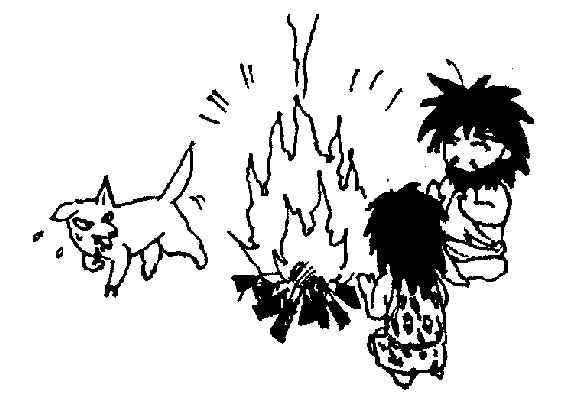演示実験で燃焼について調べる
演示実験の内容
(最初の講義のとき配布する「演示実験の解説」を参照)
1 気化熱による冷却作用(1)────── 燃えないハンカチ
2 気化熱による冷却作用(2)────── 指ロ−ソク
3 引火点と引火 ──── 灯油と天ぷら油にマッチで火をつけられるか
4 酸化鉄(鉄鉱石)から鉄をつくる ──── テルミット反応
5 水の中で燃える火 ─────────── 酸化剤として働く水
6 圧力による赤リンの発火 ──────── 自然発火(1)
7 拡散燃焼 ────────── 燃焼状態から物質の構造を推定する
8 予混燃焼 ────── 人類が創造した燃焼
─── 冷やすと燃えやすくなる場合と温めると燃えにくくなる場合
9 金属原子による炎の着色 ── 原子発光(炎色反応)── 花火の色
10 触媒燃焼 ─────────── 白砂糖は燃えるか燃えないか
11 砂糖の自然発火 ──────────── 自然発火(2)
12 酸化剤(KMnO4)と還元剤(グリセリン)の混合 ── 自然発火(3)
13 引火のしやすさと気体の比重 ── プロパンガスが爆発しやすい理由
14 超微粒子状鉄の反応性 ── 粒子の大きさと燃焼性(4)-- 自然発火(4)
15 粉塵爆発の可能性の実証 ────── 粒子の大きさと燃焼性(2)
演示実験と燃焼実験の意義
この授業の主な目的は、自然科学的な常識を豊かにすることとともに、学生諸君に物質へ興味をもってもらうことである。そのためには、学生諸君の感性に訴える授業が必要であろう。こう考えて、授業に演示実験を取り入れることにした。
この授業で行われる演示実験には燃焼に関するものが多い。なぜ燃焼反応なのか。無数にある化学反応の中で、燃焼反応は特別なものだ。
燃焼は、最も日常的に起こる化学反応だ。それだけではない。燃焼は、目、耳、鼻、皮膚といった五感のすべてではっきりと感じることができるただ一つの化学反応だ。他にはそのような反応はない。この意味においても、燃焼反応こそが化学反応を代表するものにふさわしい。
さらに、化学の歴史においても、燃焼の占める役割は大きい。「火は化学の始まり」という言葉がある。化学は物質の構造・性質・変化を扱う学問だ。だから、火によって物質を変化させる調理や土器作りは、化学の、否、科学・技術の始まりといえる。火はまさに文明の母だった。
火は現代のわれわれにとっても貴重なものだ。しかし、昔の人々にとっては、更に貴重なものだった。昔から太陽と火とは、われわれの生命と生活に直接的にかかわるものとして、特別視されてきた。礼拝の対象になっていたことも多い。例えば、拝火教(ゾロアスタ−教)やエジプトやインカ帝国の太陽神など。
また、火の使用は人類を他の生物から区別する最大の要素でもあった。人類と動物を区別するものは3つあるという。それは、道具の使用(一説によれば、道具を作るための道具の使用)と文法のある言葉の使用と火の使用だ。
しかし、道具は類人猿も使う。道具を使うのは人類だけではない。また、前期旧石器時代人は言葉を知らなかったという。だからといって、彼らが人類でなかったとは言えない。しかし、火を使うのは人類だけだ。そして、すべての人類は火を使ったと思われる。
このように、火の使用こそが、最も明快に人類を定義するものではなかろうか。火の使用について、ギリシャ神話は次のように物語っている。
人間を創造したものでもあり、また人間の最良の友でもあったのはタイタン族(巨神族)のプロメテウス(「先に考える人」の意)であった。オリンポスの主神ゼウスは、彼とその弟エピメテウス(「後から考える人」の意)に命じて、地上に住むべき生き物たちを創らせた。
プロメテウスが神々に似せて入念に人間を創っている間に、エピメテウスは全ての他の動物を手早く創りあげ、生きるのに必要な能力を次々に与えてしまった。例えば、速く走るためのひずめや、空を飛ぶための翼などを。そのため、プロメテウスが人間を創り終わった時には、もはや人間のために与えるものが何も残っていなかった。
人間は体温を保つための毛もなく寒さに震え、牙もなく獣からの攻撃におびえていた。プロメテウスは、そのような人間の惨めな生活を見るに耐えず、ゼウスが怒るであろうことを承知の上で、オリンポスの太陽神の火を吹く2輪車の車輪から、火を盗んできて地上の人間たちに与えた。
このプロメテウスの贈り物によって、人間は初めて他の動物以上のものになった。その火のおかげで、人間は、すべての他の動物を征服するための武器を作り、土地を耕す道具を作り、また寒さと夜の暗さをしのぐ方法を知った。さらには、それらを基に、文明をも創り出していった。
激怒したゼウスは、プロメテウスを捕らえ、コーカサスの山の岩に鎖で縛りつけた。昼には鷲が彼の皮膚を突き破り肝臓をついばんだが、夜になり夜露が降りると、また皮膚と肝臓が再生した。だから、彼の苦しみはいつまでも続いた。
ゼウスの怒りは火を得た人間にも及んだ。神々は、好奇心の強い女、パンドラに封をした箱(壺という説もある)を持たせてエピメテウスにせて作られた最初の人間の女性であり、名前の意味は「神々の贈り物」だ。
エピメテウスは、兄のプロメテウスから「ゼウスの贈り物には気をつけよ」と警告されていたにもかかわらず、パンドラの美しさに目がくらみ、パンドラを受け取ってしまった。
パンドラは、ある日、好奇心に駆られて箱の封を破り、箱を開けてしまった。箱から出てきたものは、それまで人間が知らなかった強欲、虚栄心、嫉妬、中傷といった全ての害悪の根源であった。怪しい気配に驚いてパンドラがあわてて閉めた箱に、再び閉じ込められたものは「希望」だけであった。(こうして「黄金時代」は終わった。)
火を手にすることによって余りにも神々に近づき過ぎたために、人間はこのように罰せられた。古代ギリシャ人達は、火の使用こそが人間を他の動物に卓越させたものであり、神々にすら脅威を与えうる存在にした、と考えたのだ。
しかし同時に、火は恐ろしい災いをもたらすものでもあった。火は人類を守り文明を育てるものであると同時に、全てを破壊し尽くすものでもあった。それは戦争や火災のことを考えれば分かる。このような火の光と陰、表と裏の二面性を、古事記、日本書紀に記された日本神話は次のように物語っている。
万物の祖神であるイザナギ、イザナミの二人の神々は、大八島の国々(日本列島)を産み、さらに多くの神々を産んだ。その中の一人に、火の神であるヒノカグツチがあった。
母であるイザナミは、ヒノカグツチを産むときに、その火の神のもつ火に焼かれて重い火傷を負った。死の床に伏したイザナミの苦しみの中から、火によって導かれる鉱山と鉱業の神、焼き物の神、農業の神、そして火の暴威を抑えるための水の神が生まれた。
火の神を産んだために万物の母であるイザナミは死んだ。この神話は、産みの母をも焼き殺してしまう火、すなわち制御できない火の恐ろしさを物語っている。
われわれもまた、火の恐ろしさにも深く注意をはらいながら、化学反応としての燃焼の魅力を探っていこう。とにかく火遊びは面白い。子供も火遊びは大好きだ。江戸の華であった火事には、人々を興奮させるものがある。
火遊びこそは、化学のロマンの、否、科学のロマンの原点と言えるものであろう。本講では、「燃焼」という章を設けず、実験で燃焼について学ぶ。
各実験の解説 トップページにもどるには左欄上部の文字をクリック